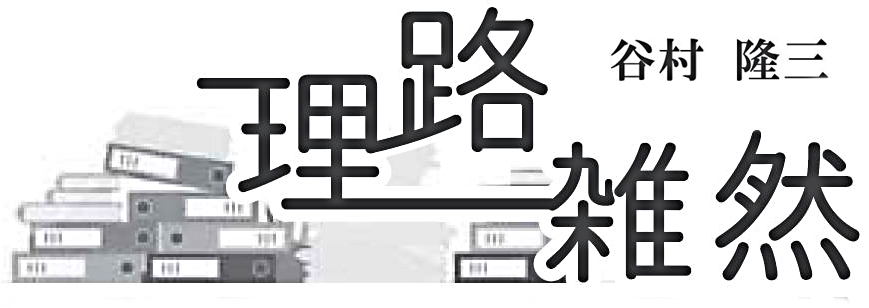理路雑然―186―
2021年10月16日(土)
特集記事
理路雑然
理科の実験でやったが、ビーカーに入れた水の中に砂糖を入れかき回すと、ある量以上は溶けずに底に溜まる。これを飽和といい、その限界を飽和点と教わった。人も同じように飽和点がある▼限界を超すと、鈍感になる、飽きるという心的飽和だ。新型コロナ感染拡大に対し政府は、緊急事態宣言とかまん延防止等重点措置を相次いで発し延長してきた。県や市からの協力要請も同時にあり、聞く方は混乱する。専門家の難しい話も重なり、もういいという状態に陥り麻痺する▼気象庁の気象災害のアナウンスは、大雨、大雪、暴風、風雪、波浪、高潮、雷、濃霧、乾燥、なだれなどそれぞれに、特別警報、警報、注意報がある。避難指示は警戒レベル1(心構え)から、警戒レベル5(災害が発生・切迫)があり、気象庁発表と自治体発表がある。またテレビだと国、県、市それぞれが入り交じり、映像が繰り返し流されるため、すぐに心的飽和点に達する。自然災害の報道も同様な傾向がある▼加齢による脳の老化が大きいそうだが、若い人も同様に心的飽和は起きる。幸せも悲しみも、グルメも美酒も美男美女も、勝利の喜びも怒りも、危機感も雄弁もなにもかも飽和点がある▼しかし、ビーカーの水の温度を上げると溶ける砂糖の量は増える。限界点はやり方次第で大きく変化するのは人も同様だ。特に危機管理については適当な情報量を超えると逆効果になる。心的飽和を考慮し、簡単で分かりやすく、くどくならないようにする必要がある。我々も日頃、自分と相手の心的飽和点を意識しておくと役に立つかも知れない。