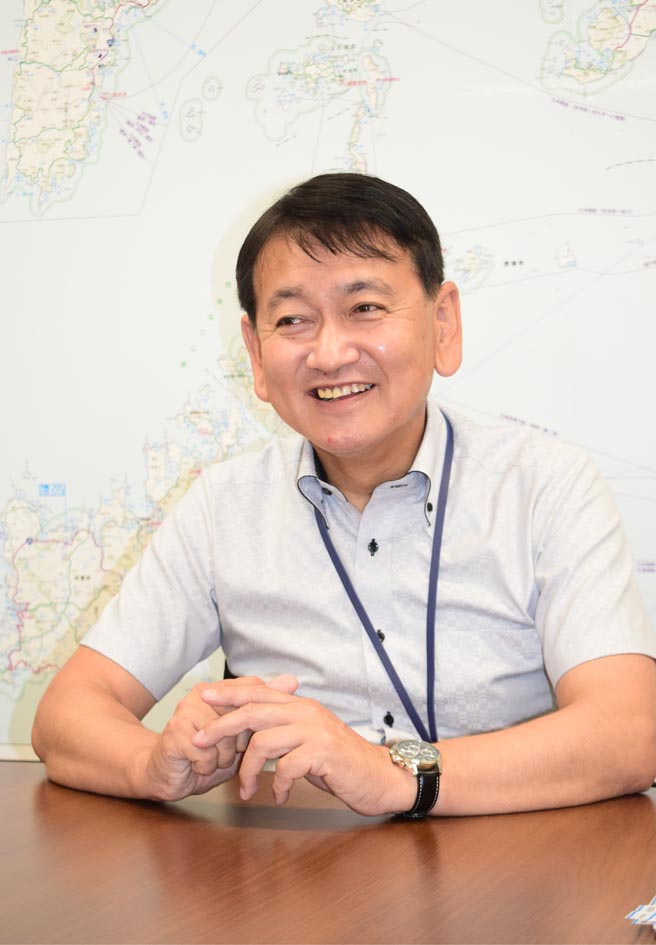【行政トップインタビュー】
県土木部植村公彦技監に聞く/建設業の持続的発展を支援
2024年08月21日(水)
特集記事
人物
就業者の高齢化と若手の担い手不足などで、働き方改革への対応が求められる中、時間外労働の上限規制が適用されるなど、さまざまな課題に直面している建設業界。都市計画やまちづくりに長く携わり、入庁30年目の2016年度に建設企画課の総括課長補佐に就いたことで、「土木行政に関する自分の世界が大きく広がった」と話す土木部の植村公彦技監は、土木部の使命を“インフラの整備・維持更新を通した県内各地の活力向上と県民の安全安心確保”とし、その実現のための目標の一つに“建設業の持続的発展に対する支援”を掲げている。具体的にどのような取り組みを進めようとしているのか話を聞いた。
“地域に不可欠な存在”を共通認識に
まず、建設業の支援の考え方について
「インフラ整備と災害対応の最前線を担う建設産業は、地域にとって不可欠な存在であることを、県民の共通認識として形成することが第一。その上で、人材の確保育成や生産性向上、適正な利益の確保を後押ししていく。従来の取組に加え、社会情勢の変化や業界からの要望を踏まえて適時適切に対応していく」
持続的発展には事業量の安定的な確保が不可欠。
国土強靱化5カ年加速化対策後を見据えた中長期的な対応は
「長崎は離島や半島が多いだけでなく、土砂災害警戒区域が全国2番目の数など、土木行政を進める上で厳しい条件を抱えている。能登半島地震では、インフラが壊滅的な被害を受け、孤立地域が発生したが、長崎でも同様の状況になりかねない。事前の防災・減災を進めることが重要だと改めて認識した。現在は、国土強靱化対策の別枠予算により、集中的なインフラ整備ができているが、まだまだ整備すべき箇所が数多く残っている。加速化対策後も、強靱化を進めていけるよう、国に対し、新たな対策による予算・財源の確保と県への配分を強く要望していく」
インフラの維持も中長期的な視点で取り組まねばならない
「これまで整備してきた大量の公共インフラの機能を長期的に維持し、長く使い続けることが求められている。本県では、施設に不具合が生じてから対策する〝対症療法〟から、定期的な点検で、不具合が生じる前、または小さいうちに対策する〝予防保全〟的手法に移行して、施設の延命化とライフサイクルコストを縮減するため、08年に全国に先駆けて『長崎県橋梁長寿命化修繕計画』を策定。その後、さまざまな公共施設の維持・補修計画を策定してきた」
「橋梁については、海上に架設された鋼製長大橋が多数あり、潮風による腐食を受けやすい環境下で、今後急速に老朽化することから、さまざまな新技術を活用して、これまで以上に効率的・効果的な維持管理の実施が必要となっている。この観点から、県管理橋梁のうち、西海橋や平戸大橋など支間長200㍍超の7つの鋼橋を対象に、高度な技術力やノウハウを持つ民間企業に長期間包括的に維持管理業務を委託し、高度な予防保全を実施できないか考えている。21年度~22年度の『インフラの維持管理に係る官民連携事業の導入検討支援』で国土交通省総合政策局が導入可能性調査を実施し〝一定の可能性がある〟との結果を得ているので、今後、民間事業者に対する個別ヒアリングや勉強会を県が行い、事業実施に向け検討・調整する予定である」
事業量の確保と併せて、不調・不落対策も重要
「23年度の土木部の不調・不落率は2・8%で、前年度比1・5%減。国土強靱化で予算が一気に増えた数年前に比べると落ち着いてきたとの認識だ。不調・不落の主な原因は、施工体制の構築や下請けの確保、技術者の配置が困難といった〝人手不足〟。このほか▽手間がかかる▽規模が小さい▽施工箇所が点在▽現場状況に工事額が合わない―などがある。県では〝人手不足〟に対し、発注ロットの拡大や余裕期間制度の活用、発注時期の平準化などを実施。また、実際の施工状況に合った適切な設計・積算に向け、設計段階から施工業者(建設業協会など)に参画してもらって施工方法を一緒に検討したり、積算の際に施工業者に見積もりを出してもらうなどの取組をしている。ただ、業界側からは、まだ不十分との指摘があるので、国や他県の対策なども参考にしながら検討を深めていく」
建設業界にとって一番の課題と言える担い手確保への取組は
「県内建設業の就業者は、50歳以上が5割を超える一方で、30歳未満は僅か1割。今後、高齢層の大量退職が想定される中、担い手の確保は喫緊の課題。学校基本調査では、23年3月の高卒者の県内建設業の就職率が60・4%で、5年前より6・8ポイント上昇しているが、長崎労働局によると23年3月卒の県内建設業の充足率は16%で、他産業よりかなり低く、担い手不足の状況だ」
「これまでも、工業高校の生徒を中心に、現場見学会や卒業生による講和などを行い、建設業のやりがいや使命感を伝えてきた。加えて22年度には、県内建設業の魅力や就職情報を発信するポータルサイトを構築。先進的な取組や若手技術者のインタビューを掲載するなどして、3Kのイメージを払拭し、誰もが働きやすく希望が持てる業界であることを、若い世代に積極的にアピールしている」
「さらに、若年層や女性の確保・定着には、建設業の経営者自らが就労環境改善や働き方改革を進める必要があるとの考えで、22年度から長崎建産連と共催し『建設企業経営者向け意識改革セミナー』を開催。この成果もあってか、複数の県内企業で新たな取り組みが進み始めている」
若手人材の確保には休日の増加はじめ職場環境の改善が重要
「県では、15年度から週休二日モデル工事(4週6休以上)を導入。23年10月からは、従来の『受注者希望型』に加え、週休二日を義務付ける『発注者指定型』の2種類とした。実施数は、初年度の3件から、23年度には885件まで増加。しかも、ほとんどが4週8休だ。国が、週休二日の〝質の向上〟として、工期全体を通した4週8休の確保から月単位での週休二日を掲げ、補正係数を設定したことから、県としても同様の対応に向けて調整しているところだ」
早ければ今秋にもDXアクションプラン公表
時間外労働の上限規制適用で、生産性向上が一層求められている
「県内の建設業は、10年前と比較して年間の総労働時間と出勤日数は短くなっているが、他産業よりは長い。長時間勤務は、必然的に時間外労働の発生が予測されるため、一層の対策が必要。具体的には、前述の週休二日推進や意識改革セミナーに加え、DX化や工事書類の簡素化がある」
「ICT施工・DX化による生産性向上・省力化は、これまで以上に強く求められている。県では15年度から、県内建設企業の技術者を対象にICT活用工事の現場見学会を、経営者向けにも意識改革セミナーで先進事例を紹介。遠隔臨場や情報共有システムによる省力化や効率性向上を推進してきた。本年度、建設企画課にインフラDX推進班を設置し、建設生産プロセスの各段階でICT技術を活用した取り組みを進めていく。現在、目指す姿を示し、実装に向けたプロセスや具体的取組を明記した『アクションプラン』を検討中。今後、業界の意見を聞きながら早ければ今秋にも公表し、DXを一層進めていく考えだ」
最後に県内建設業者へ向けてメッセージを
「建設業の皆さんはインフラ整備や維持更新、災害対応の上でなくてはならない頼りがいのあるパートナー。だからこそ、業界の持続的発展を使命の一つに位置付け、様々な取組を連携して進めてきた。23年に最低制限価格を引き上げる際、建設業協会が『新3K実現へのアクションプラン』を定め、従業員の処遇改善や働き方改革などに着手し、わずか1年で4%を超える給与水準の向上や技術者数の増加などの成果を挙げた。その実行力に最大限の敬意を表したい」
「社会経済情勢が刻々と変化する中、今後も現行施策・制度の課題が出てくる可能性がある。その際には、互いの立場を尊重しつつ、協力して解決策を検討することが肝要だと思う。すべての要望に応えるのは無理かもしれないが、どうすれば全体がより良い状況になるかを判断基準に、しっかりコミュニケーションを図っていきたい」